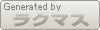クリックで画像表示
|
基礎体温
基礎体温とは、生命維持に必要な最小限のエネルギーしか消費していないと安静状態にあるときの体温のことを言います。つまり、寝ているときの体温になるのですが、寝ている間は体温測定が自分ではできないので、朝目覚めてすぐの体温ということになります。
ただし、人の身体が安静状態になるのは、5時間以上しっかりと睡眠をとった場合。5時間未満の睡眠の場合は、その体温は正確な基礎体温とは言えません。
婦人科を始めて受診する前の2、3か月は基礎体温を測定し、受診時に基礎体温表を持参しましょう。
(基礎体温のはかり方)
一般の体温計ではなく、婦人体温計を使用します。
①寝る前にすぐに手が届くところに婦人体温計を準備する
②起きたら体を起こす前に体温を測る
③基礎体温表に記入する
前日お酒を飲んだ・夜中に起きたなど変わったことがあれば記入しておく
(基礎体温からわかること)
・排卵しているかどうか
・黄体機能不全ではないか
(正常な基礎体温)
・低温期と高温期の2相性になっている
・低温期と高温期の差が0.3度以上ある
・高温期が10日以上ある
・低温期から高温期への移行が1、2日ぐらいで行われている
基礎体温は自分の身体を知るバロメーターになりますので、妊活中はつけてみてもいいでしょう。
ただし、基礎体温を測ることがストレスになるようでしたら、絶対に測らなければならないものではありませんので、測るのを中断してもよいと思います。
|

クリックで画像表示
|
超音波検査
婦人科のエコーは膣からのエコー(経膣エコー)になります。
細い棒状のエコーを膣から挿入しますが、痛みはほとんどありません。
(この検査で分かること)
・卵胞の大きさ
・子宮内膜の厚さ
・子宮筋腫やポリープの有無
・排卵したかどうか
一般的に卵胞径が20ミリになると排卵するといわれていますので、この検査によって卵胞の大きさを確認し、おおよその排卵日を予測することができます。
|
子宮卵管造影検査
子宮卵管造影検査は、膣から器具を挿入し、子宮~卵管~腹腔内に造影剤を注入し、レントゲンを撮影します。
卵管が狭くなっていたり、詰まっていたりすると、痛みを伴うことがあります。
ほとんどの病院では事前に鎮痛剤が処方されます。
水溶性の造影剤を使用した場合は1日で終了しますが、油性の造影剤を使う場合は2日かけて検査します。
発泡剤とエコーを使った卵管造影検査もありますが、保険適用ではないので自費となり1万円程度かかります。
(この検査で分かること)
・子宮形態異常
・卵管の疎通性
・卵管采の疎通性
この検査は造影剤を通すことにより、子宮や卵管の疎通性をよくするとともに、造影剤の殺菌作用で、検査後妊娠しやすくなる場合があります。
「造影後のゴールデンタイム」と呼ばれており。効果は半年続くと考えられています。
卵管が詰まっているかどうかは、その後の妊活を大きく左右しますので、子宮卵管造影検査は、必ず受けてほしい大切な検査です。 |

クリックで画像表示
|
採血(卵胞期採血・黄体期採血)
基礎検査で行う採血は2種類(卵胞期採血・黄体期採血)あります。
・卵胞期採血(月経3~5日目)
卵巣機能(LH、FSH、E2、P4)
甲状腺検査(TSH、FT4)
プロラクチン
・黄体期検査(排卵から約10日後)
プロゲステロン値
卵胞期採血では、卵巣機能がきちんと働いているか、卵胞の育ちを阻害しているものは分泌されていないか、などホルモンの基礎となる値を調べます。
卵巣機能が落ちてきていると判断された場合は、不妊治療をスムーズに進める必要があります。
甲状腺やプロラクチンの値に異常が見られた場合は、そちらの治療を優先する必要があります。
黄体期採血でプロゲステロン値が低かった場合は、ホルモン補充が必要になります。 |
子宮頚管粘液検査・フーナーテスト
・子宮頸管粘液検査(排卵時期)
子宮頸管は、子宮内に雑菌が入り込まないように、排卵時期以外は固く閉じています。しかし、排卵時期は精子を子宮内に取り込まねば妊娠しないので、少しだけ通り道を開きます。しかし、雑菌の侵入は防がねばならないため、その通り道を粘液で塞ぐのです。これが子宮頸管粘液と呼ばれるもので、この粘液の量や粘調度を調べるのが「子宮頸管粘液検査」です。
排卵日付近に診察し、子宮頸管粘液を針を外した注射器で吸い取り、量をはかり、粘調度を指で粘液を伸ばして確認します。
痛みは全くありません。
この子宮頸管粘液の量が少なかったり、粘調が強かったりすると、精子が子宮内に入りづらく、不妊の原因になります。
・フーナーテスト
子宮頸管粘液に「抗精子抗体」と呼ばれる、精子に対する抗体を持つ方がおられます。この抗体を持っているかどうかを調べる検査です。
排卵日付近に診察日を決め、その前日にタイミングを取ってもらって、子宮頸管粘液検査と同様に、針を外した注射器で子宮頸管粘液を採取します。その粘液を顕微鏡で見て、粘液の中で精子が生きて動いているかを確認します。
動いている精子がいなければ、抗精子抗体を持っているということになります。
ただし、1回の検査で判断することはありません。結果が不良だったときは数回検査をして判断します。
また、採血で抗精子抗体を調べることもできます。
抗精子抗体を持っている、ということは、子宮頸管で精子が全部死んでしまい、子宮内に侵入できる精子がいないということです。
ということは、卵子と出会うことが出来ませんので、不妊の原因となります。 |
精液検査
唯一の男性側の検査です。
一般精液検査は、精子の数や運動率、奇形率など、表面上異常がないかを調べる検査です。
現段階の精液検査では、精子の質まではわかりません。
男性に、病院の採精室で専用容器に1回分の精液を採取してもらい、その精液を顕微鏡で見て検査します。
ご主人さんが来院できない場合は、病院から受け取った容器に、ご主人にマスターベーションによって1回分の精液を採取してもらって病院に持ち込み検査することもできます。
その場合は採取から2時間以内に持ち込むこと、36度程度に保温しながら持ち込む必要があります。
精液検査が不良だった場合は、数回繰り返し検査します。
|
不妊6大基礎検査は、不妊治療を始めるにあたって、その治療を決定していくためにとても重要な検査です。どの項目も省略することなく、すべて検査することをお勧めします。
検査に関して不安なことがあれば、いつでもご相談にお越しください。